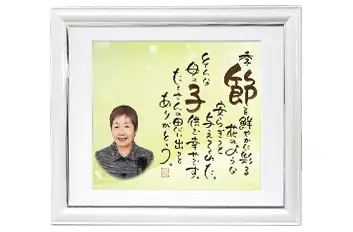お知らせ
葬儀後に控えるべきこと
~忌中と喪中の違いについて~
人生において大切な人を見送る「葬儀」を終えると、遺族の生活は大きな節目を迎えます。故人を偲ぶ気持ちを胸に抱きながらも、日々の暮らしは続いていきます。その中で「どのくらいの期間、どのようなことを控えるべきなのか」という疑問を持たれる方は多くいらっしゃいます。特に、年賀状やお祝いごとへの対応、地域のお祭りや神社参拝への参加などは、親族やご近所との関わりもあるため迷う場面が多いものです。
今回は、葬儀後に大切とされてきた「忌中(きちゅう)」と「喪中(もちゅう)」について、それぞれの意味や期間、控えるべきことを整理し、あわせて神事や祭礼への関わりについてもご案内いたします。宗派や地域の慣習によって差はありますが、一般的な考え方として参考になさってください。
~忌中とは~
まず「忌中」とは、故人を亡くしてから四十九日法要までの期間を指す言葉です。仏教では、人が亡くなってから四十九日間、魂がさまよいながら次の世界へと旅立つとされ、この期間を「忌中」と呼びます。遺族にとっては故人の冥福を祈り、静かに日々を過ごす大切な時期です。
忌中は「死のけがれを避ける」という意味も含んでおり、特に神道においては「死」を“穢れ”と考えます。そのため、忌中の間は神社への参拝や祭礼への参加を控えるのが通例となっています。家庭でも「神棚封じ」と呼ばれる習慣があり、神棚に白紙を貼って扉を閉じ、四十九日の忌明けまで神様へのお参りを休むことが一般的です。
~忌中に控えること~
・神社への参拝
死を“穢れ”と考える神道では、忌中の間は神様に近づかないことが礼儀とされています。七五三や初詣、地鎮祭などの神事も、この時期は見合わせることが望ましいとされます。
・お祝いごとや宴席への参加
結婚式や出産祝い、新築祝いなどの慶事は控えるべきとされています。特に披露宴のような華やかな場は、遺族自身も気持ちが整わず、周囲に気を遣わせてしまう可能性があります。
・慶事の贈答
友人や知人のお祝い事に際して、品物や電報を送ることも、忌中の間は避けるのが一般的です。
忌中の間は、社会生活そのものを止める必要はありませんが、「静かに過ごす」「派手なことを控える」という心がけが大切です。
~喪中とは~
忌中が終わると、続いて「喪中」という期間に入ります。喪中とは、故人を偲びながら過ごす1年間を指し、遺族が社会的な慶事から一定の距離を置く期間とされています。
この「1年」という目安は、仏教に限らず広く社会習慣として定着している考え方です。かつては親の喪中は13か月、配偶者は13か月、祖父母は150日など、親族の範囲や深さによって期間が細かく分かれていましたが、現代では多くの家庭が「1年間」として取り扱うことが一般的になっています。
~喪中に控えること~
喪中の期間に控えることは、忌中に比べると少し緩やかです。ただし、社会的な場面で配慮を求められる点がいくつかあります。
・年賀状の送付
喪中といえばまず「年賀欠礼状」が思い浮かぶ方も多いでしょう。翌年の正月に年賀状を出さない代わりに、事前に「喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきます」といったお知らせを送ります。
・祝い事への参加
結婚式やお祭りなどのお祝い事は、できるだけ遠慮するのが望ましいとされています。ただし、親しい友人や家族からのお願いであれば、相手の理解を得たうえで参加することもあります。
・派手な行事や宴席
大規模な宴会や華やかな集まりには参加を控えるのが一般的です。
喪中は「悲しみを抱きつつも、少しずつ日常を取り戻していく」期間です。完全にすべてを禁じるのではなく、節度を持った行動を心がけることが大切です。
葬儀を終えた後、遺族は「忌中」と「喪中」という二つの期間を過ごします。
忌中は四十九日までの「深い悲しみの中で静かに故人を偲ぶ期間」。神事やお祝い事は控え、静かに過ごすことが大切です。
喪中は約1年間の「悲しみを抱きつつ、日常に戻っていく過程」。慶事や華やかな行事は控えつつ、地域の慣習に応じて調整しながら生活していきます。
現代では、宗派や地域による違いもあれば、生活スタイルに合わせて柔軟に対応するご家庭も増えています。「これが絶対に正しい」というよりは、ご家族の思いを大切にしながら、周囲の方への配慮を忘れないことが一番大切なのです。
セレモニー会館タカダ
葬祭ディレクター 楠明倫